こんにちは、旅行とグルメが大好きな食べ旅(TABETABI)です♪
皆さん、🍲鍋料理はお好きですか?
鍋料理は日本全国で知られる定番の冬の季節を代表する料理ですが、定番から郷土料理、アレンジ料理まで、その具材の違いや味の違いなど鍋料理の種類は多岐にわたります。
スーパーなどでも、各メーカーから様々な味を楽しめる「鍋のもと」が見られますよね。
醤油や味噌など定番の味、石狩鍋やもつ鍋など郷土料理の味、レモンやトマトなどのユニークな味、カレーやキムチなど他国料理との融合の味など多岐にわたります。
しかし、それでもまだ私たちの知らない郷土の鍋料理が存在します。
今日は、知る人ぞ知る、青森の南部地方(八戸など)に伝わる伝統の郷土鍋料理、「せんべい汁」の専用南部せんべいをご紹介します。

青森の南部地方に伝わるかやきせんべいを使った「せんべい汁」
青森の南部地方に伝わる南部せんべい(かやきせんべい)や「せんべい汁」とは

青森県が豪雪地域である事を象徴する八甲田ゴールドラインの「雪の回廊」
本州の最北端にある青森県。
青森県は、津軽地方(青函トンネルを有する西側)と南部地方(斧の形の下北半島を有する東側)に二分されます。
なぜ東なのに「南部」?と思われたかもしれませんが、南部地方は方角を指すものでは無く、この地を代々統治していた「南部家」という武将の名から取っている為です。
南部地方とは

南部光行の肖像画。
南部地方は、平安時代後期から鎌倉時代前期にかけて活躍した南部光行を祖にもつ青森県の地域の名称です。
南部小麦や南部鉄器、南部せんべいなどが有名で、南部せんべいは南部小麦で作られ、南部鉄器で焼かれる等、いずれの名産品もつながりがあります。
南部光行は甲斐の国(現在の山梨県)を統治していた加賀美遠光の三男で、石橋山の戦いで源頼朝に与して戦功を挙げた功績として甲斐の南部牧(現在の山梨県南巨摩郡南部町)を与えられました。
このときに「南部」の姓を称し、その10年後には奥州合戦で戦功を挙げ、陸奥国糠部五郡(青森から岩手)を与えられ、ここに定住したため、青森には「南部地方」がある、というわけです。
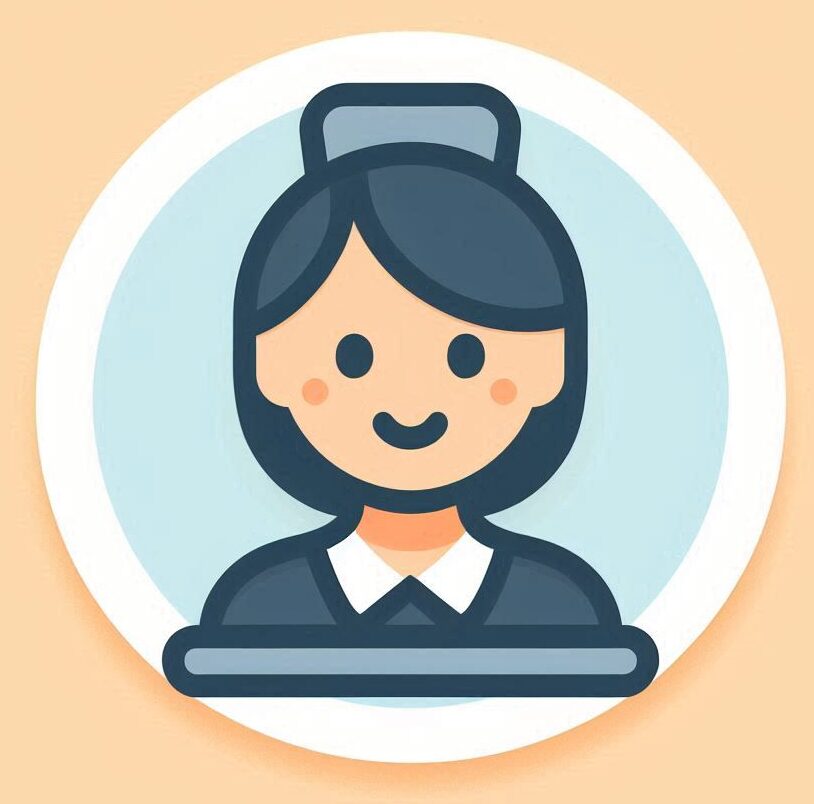
南部家は江戸時代には盛岡藩(南部藩ともいう)、維新後には伯爵家1家、子爵家2家、男爵家2家の合計5家の華族を排出し、この地を長く治めてきました。廃藩置県となった今は統治してはいないものの、南部家そのものは継続しており、企業の取締役や東北銀行の監査役など社会的に重要な立場に付いています。
南部せんべい、せんべい汁とは

写真奥にあるのが専用南部せんべい。せんべい汁をお店で食べたい時は定食がおすすめ。
南部せんべいは南部地方に伝わる郷土料理で、昔は蕎麦粉や大麦で、現在では小麦粉で作る煎餅です。
南部藩主が広めたというのもあって南部氏支配地域においては現在も非常にポピュラーな食べ物にもなっており、保存も効くため江戸時代の南部藩の野戦食だったとも考えられています。
一般的にはそのまま食べますが、今日ご紹介する「せんべい汁」のように、すいとんの代替として似た味と食感になるため南部せんべいを用い、現在では専用のせんべい汁用の南部せんべいも作られています。
前置きが長くなりましたが、南部地方に伝わる郷土の鍋料理「せんべい汁」に用いる専用のかやきせん(南部せんべい)をご紹介します。
【衝撃の新食感】青森八戸の冬の味覚が、あなたの常識を覆す!もちもち・シコシコ「かやきせん」が主役のせんべい汁が忘れられない一杯に!

寒い冬の夜、温かいお鍋を囲んでホッと一息つきたい時、あなたはどんな🍲鍋料理を思い浮かべますか?
深い雪に長い間包まれる豪雪地域の青森八戸では、冬には様々な具材を入れたお鍋に「かやきせん(南部せんべい)」を追加する「せんべい汁」が食卓に上がります。
キンと冷えた空気に湯気を立てて食卓に並ぶせんべい汁は青森県民の体を芯から温めてくれる特別な存在。
一体、どんな鍋料理なのでしょう?
「せんべい汁」それは冬の青森の食卓を彩る、歴史ある郷土料理

「せんべい汁」は、知る人ぞ知る青森八戸の郷土料理です。
江戸時代後期の天保の大飢饉の頃に食材が不足した八戸藩内で生まれたとされ、その後200年程に渡り南部地方一帯で食べられてきました。
厳しい冬を乗り越えるために生まれたこの料理は、今もなお、「冬の青森の食卓」に欠かせない人々の心を繋ぐ温かい郷土料理として愛され続けています。
せんべい汁には、南部煎餅の中でも専用に焼き上げた「かやき煎餅(おつゆ煎餅・鍋用煎餅)」を用いるのが一般的です。
これを手で割り、醤油や味噌、塩に鶏や豚を加えた出汁でごぼう、きのこ、ネギ等の具材と共に煮立てた鍋に入れます。
出汁を吸った煎餅は「すいとん」の歯ごたえを強くしたような食感となり、一口食べたら忘れられなくなるような、もちもち・シコシコの新食感を体験できます。
今日ご紹介する、この「かやきせん」は青森南部の歴史と人々の知恵が詰まった「せんべい汁」を、ご家庭で手軽に楽しむための専用の南部せんべいです。
冬の寒さが厳しい青森の人々が昔から大切にしてきた温かい食卓を、遠く離れたあなたの食卓でも再現できるのです。
常識を覆す「もちもち・シコシコ」食感の秘密

と聞いて、少し驚いた方もいるかもしれません。
しかし、せんべい汁に使われる「かやきせん」は私たちが知っている、ゴマやピーナッツの皮が含まれるお菓子の「南部せんべい」とは別物です。
この「かやきせん」は、せんべい汁に特化して作られており鍋に入れて煮込むことで、その真価を発揮します。
熱い鍋の中で煮込まれた「かやきせん」は硬かった生地が徐々に水分を吸い込み、もちもち・シコシコとした独特の食感に変化します。
その食感は「すいとんの歯ごたえを良くしたような食感」と表現され、モチモチでありながらも、しっかりとコシがあり、噛むほどに小麦の風味が口の中に広がります。
これまでにない新食感が一度食べたら忘れられなくなる、やみつきになる美味しさの秘密なのです。
出汁を吸って旨味が凝縮!忘れられない「かやきせん」の魅力

「かやきせん」の魅力は、その食感だけではありません。
このせんべいには、小麦粉で出来ており、鍋に入れる事で出汁をたっぷりと吸い込みます。
鶏肉やきのこ、ごぼうなどの具材から出た旨味が凝縮された熱々の出汁に「かやきせん」を投入すると、せんべいはその出汁を吸い込み、旨味がたっぷりと染みこんだ「すいとん」のような状態になります。
出汁の風味と、もちもちとしたせんべいの食感、そして噛むほどに広がる小麦の甘みが一体となり、一口食べるごとに深い満足感が得られます。
この「旨味がたっぷりしみこんだせんべい」は、まさに忘れられなくなるような、心温まる味わいです。
究極の手軽さ!届いたらすぐに「せんべい汁」の感動を

この「かやきせん」は、ご家庭で本格的な「せんべい汁」を味わうために、誰でも簡単に調理できるのが魅力です。
作り方はとっても簡単。
お好みの鍋の具材と、熱々の出汁を用意し、最後(一般の鍋ならネギを入れるタイミング)に「かやきせん」を堅い耳から順に割り入れて煮込むだけ。
あとは、お好みの硬さになるまで待つだけです。
この手軽さで、まるで青森の料亭でいただくような、本格的な「せんべい汁」を再現できるのです。
たっぷりと出汁を吸い込んだ奥深い旨味。
そして、冬の青森の歴史と温かさが詰まった、特別な南部せんべい。
「かやきせん」は、単なる鍋の食材ではなく、青森の歴史と知恵、そして食文化を愛する人々の情熱が凝縮された伝統料理なのです。
そんな、せんべい汁用かやきせんは以下の南部せんべい専門オンラインショップでお買い求めになれます。
|
知る人ぞ知る八戸の郷土料理! |
まとめ
いつものお鍋に、この「かやきせん」を加えてみませんか?
一口食べれば、その新食感と心温まる味わいに魅了されるはず。
「せんべい汁」を出すお店は八戸に集中しているものの、東京や神奈川などでも数店舗存在します…が、ほんの数店舗。
おそらく青森に行った事が無い方は召し上がった事が無いでしょう。
懐かしいような新しいような不思議な美味しさのせんべい汁。
豪雪の地、青森の住民を長く支えてきた、この郷土料理をぜひ味わってみてください。




